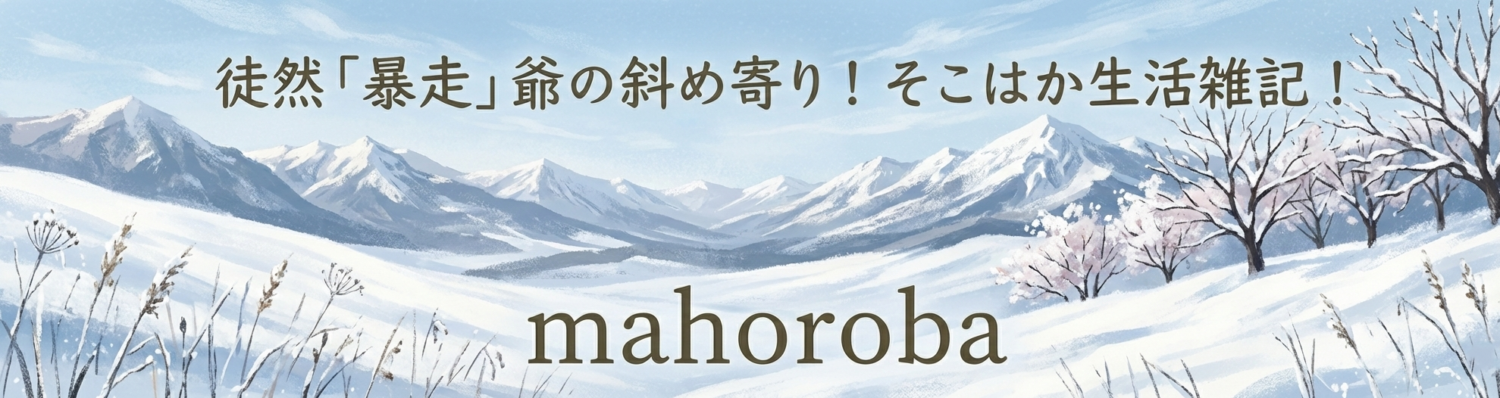そもそも “九体寺” って?
平安末期に隆盛した阿弥陀信仰では、往生の程度を「上品上生」から「下品下生」まで九つに分けました。その九段階を一目で示すため、阿弥陀如来像を九体並べて祀る堂が各地に建てられ、堂そのものを 九体阿弥陀堂、寺を総称して 九体寺 と呼びます浄土宗全書。現存例はごくわずか。今回は全国に3例しか知られていない貴重な九体寺をぐるりと紹介しつつ、長野県長野市若穂綿内の 蓮台寺 をメインに掘り下げます。

① 京都・木津川市 浄瑠璃寺(真言律宗)
- 創建 8世紀創始/本堂は1107年建立
- 見どころ
- 国宝の本堂(九体阿弥陀堂)と三重塔が池をはさんで東西に配置される“浄土式庭園”
- 9体の阿弥陀如来像(国宝)と四天王像が横一列に並ぶ壮観minamiyamashiro-koji.jpWANDER 国宝
池を挟んで三重塔(現世・東)と阿弥陀堂(彼岸・西)が向き合う配置は「此岸から極楽へ渡る」ストーリーを具現化。春分・秋分の日には塔から昇る朝日が堂裏へ沈む“彼岸の日の奇跡”も話題ですminamiyamashiro-koji.jp。

② 東京・世田谷区 浄真寺(浄土宗)
- 正式名称 九品山唯在念佛院浄真寺
- 開山 延宝6年(1678)珂碩上人
- 特色
- 「上品・中品・下品」の三堂に3体ずつ阿弥陀像を安置=合計9体
- 広い境内の参道両側に伸びる老樹と紅葉の名所、毎年4月の「お面かぶり」行事も人気九品山 唯在念佛院 浄真寺
都心から東急大井町線・九品仏駅を降りてすぐ。江戸時代の境内配置がほぼそのまま残る貴重な寺町オアシスです。

③ 長野・若穂綿内 蓮台寺(真言宗智山派)
歴史の輪郭
天平年間(奈良時代)に開かれたと伝わる古刹。阿弥陀如来9体を祀るも江戸時代の火災で8体が焼失。現存1体は重要文化財として本堂裏の収蔵庫に安置されていますアソビュー!Go NAGANO。

見どころベスト5
| 見どころ | ひとこと | プチ情報 |
| ① 九体阿弥陀のご本尊 | 焼失を逃れた1体は鎌倉初期様式。静かな宝物殿で対面可 | 内部は撮影禁止なので心に焼き付けて |
| ② 仁王門と新旧仁王像 | 焼失後に再建された仁王像が山門を護る | 焦げた旧像も境内で見学可 |
| ③ 紫陽花の回廊 | 地元有志が植えた約2,300株、6月中旬〜7月上旬が見頃 | 別名「信州あじさい寺」 |
| ④ 階段アプローチ | 山腹に続く石段。冬季は日陰で凍結注意 | 熊出没看板あり、鈴推奨 |
| ⑤ 六地蔵と鐘楼門 | 静けさ漂う山中で鐘を撞ける貴重な体験 | 参拝者が少なく貸切気分 |
アクセス
- 長野自動車道「須坂長野東 IC」から車で約20分
- 須坂市中心部から徒歩遠足なら往復30 km超(筆者は小学生時代に踏破!)
公共交通は不便なのでマイカーかレンタカーがおすすめ。門前に無料駐車場(大型10台)ありアソビュー!。

季節の楽しみ
- 初夏 紫陽花と新緑
- 盛夏 蝉しぐれを聞きながら涼しい本堂へ
- 晩秋 参道のカエデが燃えるように色づく
- 厳冬 雪化粧の本堂は幻想的(ただし長靴必須)

ブロガーのひとこと
子どもの頃に遠足で訪れた思い出の寺へ、定年後ふらりと立ち寄ったら、まさかの「九体寺」だった――。京都単身赴任中に10回以上通った浄瑠璃寺、東京勤務で足繁く通った浄真寺。その“兄弟”が、故郷の山中で静かに佇んでいた事実に胸が熱くなりました。

まとめ:ひっそり残る“第三の九体寺”を訪ねて
- 現存する九体寺は3か寺だけ――京都・浄瑠璃寺、東京・浄真寺、そして長野・蓮台寺。
- 阿弥陀九品思想を体感できる貴重な文化遺産。
- 蓮台寺は観光地化されていない分、静寂の中で仏と向き合える“究極の穴場”。
京都や東京に比べればアクセスは大変ですが、その分得られる心の充足感はひとしお。ぜひ九体三兄弟を制覇し、「極楽浄土への旅」を体感してみてください。
次回は蓮台寺参拝コースと近隣グルメを紹介予定。お楽しみに!