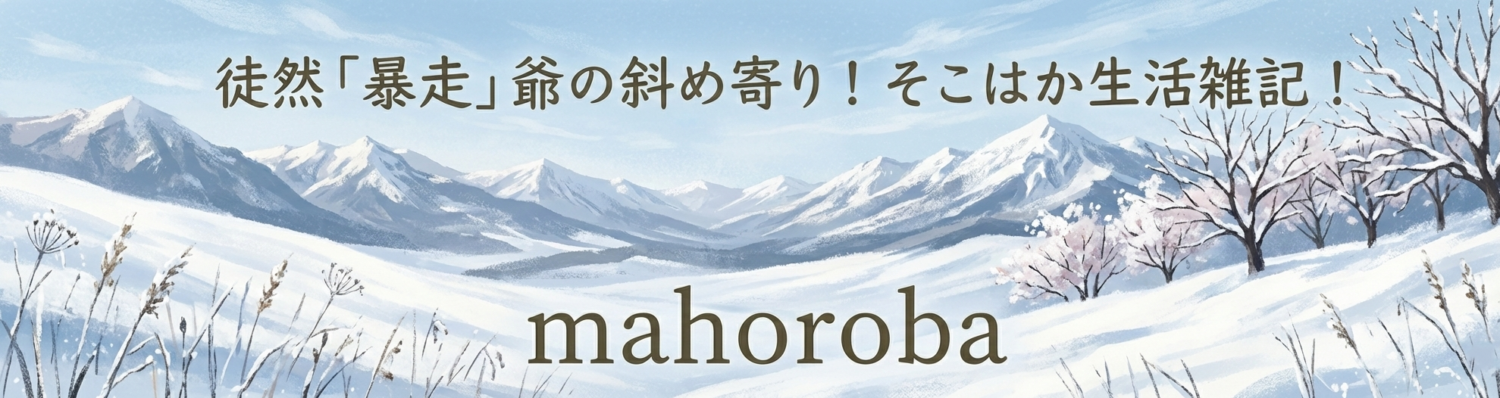長野市真島町――千曲川と犀川に挟まれた川中島の地に、静かに佇む「清水神社」。この神社は、地元の人々にとっては馴染み深い存在でありながら、その由緒や格式を知る人は意外と少ないかもしれません。今回は、そんな清水神社の魅力を、歴史・祭礼・境内の末社などを通じてご紹介します。
🏞️地名と立地:川中島の歴史を感じる場所
清水神社が鎮座する真島町は、かつて「馬島」とも書かれ、朝廷に馬を納める御牧(官営牧場)があったとされる歴史ある土地です。神社は長野オリンピックの競技場「ホワイトリング」に隣接しており、アクセスも良好。長い参道を歩けば、草の香りと静寂が心を落ち着かせてくれます。
📜延喜式内社としての格式と由緒
清水神社は、延喜式内社として「信濃国更級郡十一座」の一座に数えられる格式高い神社です。もともとは「蔵王権現」と称され、産土神として地域の人々に崇敬されていました。寛政9年(1797年)に京都・吉田家の許可を得て「清水神社」の名を正式に受けた由緒があります。
主祭神と配祀神
- 広国押武金日命(第27代 安閑天皇)
- 速秋津比古命・速秋津比売命(水の神として治水に関わる神々)
この神々の組み合わせからも、清水神社が「治水の神」として信仰されてきたことがわかります。
🔥災害と再建の歴史
清水神社は幾度も災害に見舞われながらも、その都度再建されてきました。
- 享保5年(1720年)犀川の大洪水で社地流失
- 永禄7年(1564年)川中島合戦の兵火で焼失
- 寛保11年(1742年)再び洪水で流失
これらの困難を乗り越え、現在の地に移転し、明治6年には村社に列せられました。
🎉祭礼と氏子の信仰
清水神社では、年間を通じて以下の祭礼が行われています:
| 月 | 祭礼名 |
| 1月 | 歳旦祭 |
| 4月 | 祈年祭 |
| 9月 | 風鎮祭 |
| 10月 | 例祭・末社祭(真島六組による太神楽奉納) |
| 11月 | 新嘗祭 |

特に10月の例祭では、地元の六組が太神楽を奉納するなど、地域の信仰心が今も息づいています。氏子の皆さんの厚い信仰が、神社の静かな力強さを支えているのです。
🪷境内の末社と石像たち
清水神社の境内には、金比羅神社をはじめとする多数の末社が点在しています。石像の数も多く、まるで小さな神々の森のよう。
代表的な末社の一部:
- 金比羅神社:航海・交通安全の神として知られる
- 稲荷社:商売繁盛・五穀豊穣を祈る
- 八坂社:疫病除けの神
- 天神社:学問の神、菅原道真公を祀る
それぞれの社が、地域の生活に密接に関わる願いを象徴しており、参拝するたびに異なる祈りの形が見えてきます。
🙏参拝のひとときに
私自身、仕事で早く着きすぎてしまったある朝、時間調整のためにこの神社を訪れました。罰当たりにも程があるかもしれませんが、静かな境内で手を合わせると、心が整っていくのを感じました。
地元の方でも、清水神社の由緒や祭神について詳しく知らない方も多いかもしれません。ですが、こうした歴史と信仰の背景を知ることで、より深く神社と向き合えるのではないでしょうか。
🏁まとめ
清水神社は、格式ある延喜式内社でありながら、地域に根ざした温かい信仰の場でもあります。真島の歴史、災害を乗り越えた再建の物語、そして今も続く祭礼と末社の祈り――そのすべてが、静かに語りかけてくるようです。
次に真島を訪れる際には、ぜひ清水神社の参道を歩いてみてください。きっと、心に残るひとときになるはずです。