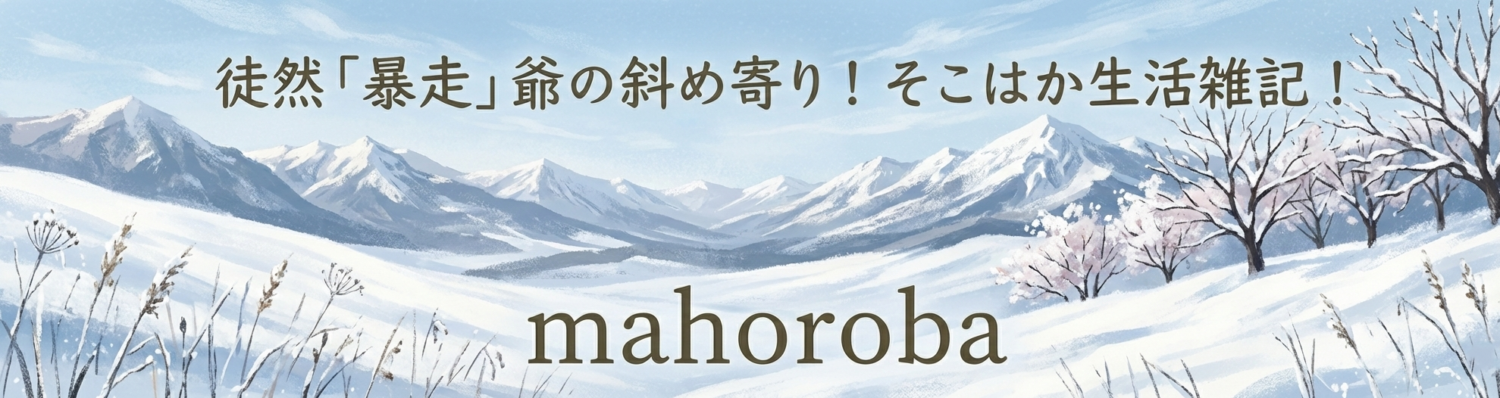須坂市本上町・三社神社――町を見守る三柱の神さま物語

1. 産土神(うぶすながみ)としての三社神社
須坂市には 70 余りの町内会があり、それぞれが“産土神”――その土地に暮らす人々の幸いを守る神さま――をお祀りしています。本上町では、かつて町内の三か所に鎮座していた秋葉社・八幡社・皇大神宮を一つの社に合祀し、「三社神社」として町民の心のよりどころにしてきました。町総鎮守である芝宮墨坂神社とも深いご縁があり、例祭の祭式は墨坂神社宮司がご奉仕します。須坂マップ

2. 各お社のご祭神とご利益
| お社 | ご祭神 | ご利益・特徴 | 由来のポイント |
| 秋葉社 | 火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)ほか | 火伏せ・火難除け | 江戸時代の「秋葉講」ブームで全国に信仰が拡大し、火災の多かった町場を守る神として庶民に親しまれた。伝承怪談奇談・歴史秘話の現場を紹介|日本伝承大鑑 |
| 八幡社 | 誉田別命(応神天皇) | 武運長久・厄除け・家内安全 | 宇佐神宮を総本社とする八幡信仰は、源氏・平氏など武家に広まり、のちに庶民の守護神として全国に勧請。ウィキペディア |
| 皇大神宮 | 天照大御神 | 五穀豊穣・家内安全・国家安泰 | 三重県伊勢市の伊勢神宮〈内宮〉と同じ御祭神。太陽の神として日本国民を照らす“皇祖神”として崇敬される。ウィキペディア |

3. 合祀のいきさつ
明治の神社合祀令期に、小さな祠を一カ所へまとめる動きが全国で進みました。本上町でも地域のまとまりを強めるため、三社を現在地に集めて一社とし、「三社神社」の名でお祀りしてきたと伝わります。境内に三つの小祠が横並びに鎮座しているのは、その名残です。

4. 春・秋の例祭――町がひとつになる日
- 春例祭(4 月中旬)
- 9:00 神事:町役員・氏子代表が玉串を奉り、五穀豊穣と無火災を祈願
- 10:00 子ども会による獅子舞奉納
- 10:30 境内でお神酒拝戴
- 秋例祭(10 月下旬)
- 9:00 神事:実りへの感謝と一年の無病息災を祈願
- 10:00 神輿渡御(町内を一巡)
- 12:00 直会(なおらい):公会堂に戻り、芝宮墨坂神社宮司・町民が一堂に会して会食
直会は「神さまからのおさがりを皆で頂き、御神徳を分かち合う」場。若者からご年配まで肩を並べて杯を酌み交わし、町内の連帯感が一層深まります。

5. 町全体で守る“須坂の神まつり”文化
墨坂神社が古くから須坂の中心を守護してきたように、各町は自分たちの産土神を大切にし、春秋の祭礼を欠かしません。この重層的な神社網こそが「須坂市=祈りのまち」という風土を形づくっています。地元では「祭りの日に神社を掃除し、境内で子どもたちが駆け回る光景が町の宝だ」と語り継がれています。Skima信州-長野県の観光ローカルメディア

6. まとめ――小さな社に宿る大きな絆
三社神社は、火難を防ぐ秋葉さま、武勇と守護の八幡さま、太陽の恵みをもたらす天照大御神という、役目の異なる三柱をひと所に祀る珍しいお宮です。
春と秋の例祭で手を合わせ、直会で盃を交わす――その積み重ねが、代々の町民を結び、須坂市の繁栄を支えてきました。
本上町の三社神社に込められた祈り――ぜひ足を運んで、その空気を感じてみてください。